託される重みは冠する名に比例して
初進撃でエルリです。何を書こうか迷って結局最初に抱いたイメージのままの二人を取り敢えず書いた感じで。(初心大事よね!)
兵長の名前を呼ぶ団長が好きです。なんか、名前を連呼させるとついつい甘い方向に流れていきそうになりましたが今回は硬く!(これも一応、初志貫徹ってことで)
それが最初に届いたのはリヴァイが「兵士長」という役職に就いて2回目の璧外調査を終えた後だった。
「リヴァイ兵士長、よろしいですか」
遠慮がちに自室の扉の外から掛けられる声に、リヴァイは報告書を書く手を止めて扉を見た。
璧外調査から戻って2日、まだ後始末の為に上級兵士はもとより、いや、一般兵こそ物資の整備や点検に始まり、怪我人の手当て、そして…帰還が成らなかった兵士の部屋の遺品整理にと、忙しい時期だった。
リヴァイは逡巡した後、ペンを置いてドアに向かった。
「なんだ?」
書いている報告書は今回の調査の被害状況であり、失くした兵士の所属部隊と名前のリストを参照している所だった為、リヴァイの気分は最悪を通り越して最低だった。
つっけんどんに言いながら扉を開けたリヴァイの目に入ったのは目をギュッと瞑って震える両手で小さな―――1食分のパンの包み位の小包を差し出している新兵の姿だった。
「なんだ、これは」
宛名には確かにリヴァイの名が記されているが、それは王都からの郵便物ではなく、兵団内の移送物資の形態をしていた。
「はい、今回の璧外調査で亡くなった方の遺品整理をしていたところ、兵士長宛てのものが出て参りましたのでそれを纏めたものだそうです」
触れるとカサリと音を立ててリヴァイの手の上に乗ったそれは見た目通りに軽く、柔らかかった。
「何故、俺に・・・?」
「それは分かりませんが。確かに兵士長宛てだと」
璧外調査帰りのささくれ立っている兵士に命令されて動いているこの新兵は、あっちこっちで機嫌の悪い兵士の命を受けて仕事をしているのだろう、すっかり怖気づいてリヴァイの方をろくに見ようともしないで震えながら言われた言葉を伝えるだけだ。
リヴァイは小さく息を吐いて「ご苦労だったな」と使いの新兵を労い、ドアを閉じた。
リヴァイはかなり特異な経歴を持っているため、所謂「新兵」としての雑務をしたことが無い。
エルヴィンに拾われ、王都にある彼の別荘で個人的に立体起動装置の訓練やら兵法論やらを叩き込まれた後、訓練兵団をすっ飛ばして直接調査兵団に配属されたからだ。
こうして兵士長なんぞになってみれば、それが如何に無謀で型破りで常識外だったか判ったのだが、裏を返せばそれはそれだけ当時兵士長だったエルヴィンが璧外調査に危機感を抱き、何らかの手を打つ必要性を感じていたことが伺える。
一向に打開できない巨人との戦い。いや、巨人の優勢を覆せないでいる事は一般市民にすら明らかだった。だからエルヴィンは切り札を欲した。それも早急に。
その白刃の矢が立ったのが自分だったことについてはリヴァイは別に何の感慨も持ちはしなかったが、現在の己が果たして切り札たる能力を備えているのか、自分でも判別が着いていなかった。現に、璧外調査の結果はあまり変わり映えがしない。璧外調査の度に喪う兵の数は横ばいで、リヴァイ一人が加わったとてどうなるものでもない。それを痛感している真っ最中だというのに、当の役立たずの兵長に向かってわざわざ送るもの何なのか。
リヴァイはペン立てに挿してあったペーパーナイフを無造作に手に取り、紐を断ち切った。包みを解けばそこには乾いた血が黒く点々と跡を残す腕章が幾枚も重ねられていた。リヴァイは眼を見開いてあまりの衝撃に、机に空いている左手をついてふらついた己の躰を支えた。
―――何を、意味する?
間違いなく、これは死亡した兵士達の腕章だ。
遺体を持ち帰ることが叶わない場合、髪や遺品となる指輪やネックレス、腕章等を持ち帰る。それらは遺族の許へと丁重に送り届けるのだが、それが己の許に届けられる意味が分からなかった。
責めているのだろうか。無言の抗議というのなら、理解できる。自分が全ての兵を護れるなどと思ってはいないし、護ろうとも思っていない。自分は―――巨人を斃すことに重きを置いている。そしてそれを実行する為に、敢えて救出に行かない場合も、ある。その結果、命を落とす兵士やその仲間が自分をどう思うかなんて、火を見るより明らかだ。
「・・・恨まれるにしても・・・こう数が多くちゃ堪えるぜ?」
一瞬瞳を眇めて唇を噛みしめる。
それでも、この腕章1枚1枚はそのまま貴重な兵士一人一人だ。
リヴァイは唇を噛み締めながら順に腕章を見て行った。
腕章の裏には氏名と、所属班が書かれていた。
そしてそれら腕章の下には手紙やら写真やらが重ねられていた。
そっとそのうちの1枚を広げる。
決して上手くは無い字だった。まだ若いのか、あまり学が無いのか。それでも懸命に綴ったと思われる文面を読み進めてリヴァイは目を瞠った。貪るように次の手紙に手を伸ばす。その次の手紙にも。
「・・・くそぉ。ちくしょう。・・・俺なんかに。希望を託すなよ。―――俺を、赦すなよ・・・」
小さく零れたリヴァイの呟きが手にした紙の束に吸い込まれる。
手紙に綴られていたのは調査兵団兵士長に対する、切ないまでの希望。盲信、と呼べるかもしれない。リヴァイの立体機動を一度でも目にした者は、例外なくその華麗な技に心酔し、夢を抱く。『彼ならば』と。
彼ならばきっと巨人を根絶やしにしてくれるだろう。彼ならば、壁の無い未来を築いてくれるだろう。
調査兵団に入団した兵士は『人類の為に心臓を捧げるか?』と問われ、それに対し首を縦に振った者達だった。だから、捨て駒になれと言われればそれに従う―――怖いけれど、という内容と供に、必ず最後に『だからどうか、リヴァイ兵長、巨人の居ない未来を』と綴ってある。
「俺は。確約は出来ない。・・・でも、背負ってやる、その望みを」
リヴァイはゆっくりと再び腕章に目を落とし、書かれている名前を読み上げて行った。
そして璧外調査が回数を重ね、リヴァイの呼び名も「兵士長」から「人類最強」へと変わるにつれ。
リヴァイの許に届く遺品は数を増し、今では新兵二人がかりで木箱を運んでくるくらいだった。
「リヴァイ兵長、御届け物です」
半ば儀式と化したそれは璧外調査の度に繰り返された。
その、いつの時もリヴァイは一切の表情を殺して新兵が差し出す荷物を受け取り、そしていつの時も新兵は真近に憧れの兵士長の『人類最強』である姿を見る。
リヴァイにとってそれは、彼らが信ずる希望、『人類最強』に託した想いを受け取る儀式に他ならなかった。
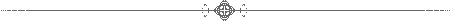
死亡した兵士の遺品整理はその班員の仕事だった。
精神的ダメージが大きすぎて軽く鬱状態とパニック状態を行ったり来たりしているエレンには任せられなくて、リヴァイは独りで遺品整理を始めた
遺族に渡すもの、始末するものを選別していて、そこに己宛ての遺書を見つけて手を止めた。
それは、細心の注意を払って、大切に、まるで壊れ物をしまうかの如くに机の引き出しの奥に、衣類の棚の一番下に、真新しい替えの制服の包みの中に、そっと忍ばせてあった。
リヴァイへの憧れ。想い。誇り。
彼らはリヴァイ自身に選ばれたと自分で知っていたから顕著なのかもしれない。けれど。
―――ああ、こんな風に。
リヴァイはそっと目を閉じた。初めて腕章と遺書を受け取った日の事を思い出す。
―――もう居ない兵士の部屋で遺品整理をして見つける、もしかしたら一度も言葉を交わしたことのない兵士長への遺品を。どうにかして渡したいと・・・渡さなければならないと・・・思うんだろうな。
不覚にも目頭が熱くなる。慌ててリヴァイは遺書から眼を逸らし、窓の外を見た。この兵舎からは壁が、近かった。
例え部屋の主が居なくとも、窓から切り取る景色は変わらない。明るい日差しを遮って暗い影を落とす、壁。巨人を遮る代償として光も、風もそこで弾いてしまう忌まわしいそれは何時かはきっと取り払うことが出来ると信じて、その為の一歩と成らんとして、彼らは逝った。
―――あの壁の無い未来を。焦がれるのは人類の遺伝子に刻み込まれた想いなのだろうか。壁の向こうのその果てに在るものを、誰も知らないというのに焦がれるのは運命か・・・。
巨人がどのくらい存在するのか。どうやって生まれるのか。それすら解っていないのに自分は希望を託される度に応え続けている。力の及ぶ限り巨人を斃すと。それで少しでも救われるなら幾らでも言うし一体でも多くの巨人を斃す。自分には喪った兵士を悼む資格は無いが今生きている兵士の絶望を和らげる力ならば在る。
リヴァイは窓の外に広がる壁を見つめながら彼らが遺した想いを強く握り締めた。
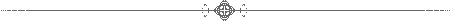
「―――エルヴィン」
エルヴィンの執務室の前でノックをしようと上げた手を止め、低く、呟くように名前を呼んだ。小さなその声、というよりも気配に反応して扉が開く。
「入りなさい。・・・報告か?私用か?」
中に入れるように体をずらして問いかけるエルヴィンの声は静かで、荒れていたリヴァイの精神を落ち着かせる。リヴァイは瞼を閉じ、一度、大きく息を吐き出してから答えた。
「報告だ」
「では、聞こう」
一歩進んで部屋の中に入ったきり動かないリヴァイをそのままに扉を閉め、エルヴィンは執務机に戻った。それでもまだ動く気配のないリヴァイに再び声を掛ける。
「リヴァイ?」
誘い込むような呼び掛けにふらりとリヴァイが足を進める。緩やかに歩を進めていたリヴァイだが、執務机の前で姿勢を正して直立起立の姿勢を取る。いつもと変わりない調子で真っ直ぐにエルヴィンを見つめながら口頭報告を始めた。
「第57回璧外調査報告。右翼索敵班初列以降全滅、被害30名。特別作戦班被害4名。移送対象生存。伝達班被害・・・」
まるで報告書を読み上げているように澱みなく言葉を紡ぐリヴァイの瞳は、しかし真っ直ぐにエルヴィンに据えられたままだった。何の感情も浮かべないリヴァイの視線をエルヴィンは真正面から受け止めていた。
「立体起動装置損傷48、うち廃棄処分16。・・・以上だ」
沈黙が室内に落ちた。傾いた陽が窓から差し込み、室内の薄暗さとは裏腹にリヴァイの足元に光の陽だまりを作る。オレンジ色のその光は、柔らかくも何処か物悲しげで、知らずリヴァイは足元に視線を落とした。
いつになく、躰の奥底に鉛を抱えているような重さを感じ、ふとこのまま何も考えずに移り往く光を見ていたい―――そう思うリヴァイは自分では気付かない、気付こうともしない精神の疲弊を抱え込んでいた。
「―――ご苦労だった。帰投後の兵の状況は」
幾許かの沈黙の後、掛けられた問いにリヴァイは視線を無理矢理足元から引き剥がした。
「昨日中に急を要する怪我人の手術は完了、故障兵としてウォール・ローゼ南部駐屯地へ移送。班別に行った死亡兵の遺品整理の完了報告を本日受けている。明日より遺族へ遺品の引き渡しを・・・」
「リヴァイ」
報告の途中でエルヴィンがリヴァイの言葉を遮った。リヴァイは小さく息を吐いて半ば開いていた唇を閉じた。
リヴァイの言葉を遮った曲に一向に次の言葉を発しないエルヴィンにリヴァイの瞳が微かに細められたが、それでも上官としてのエルヴィンの言葉をじっと待った。
「・・・リヴァイ班の遺品整理は君とエレンが?」
「、っ・・・。エレンは精神的打撃が強く、現在は地下室で半強制的に薬で眠らせてある」
一瞬言い澱んだリヴァイを見つめながら確認するようにエルヴィンが言葉を繋いだ。
「では君一人でやったんだな」
エルヴィンの強い視線に、リヴァイは己が無意識のうちに抑え込んでいる澱みの正体に気付き微かに視線を逸らした。
初めは遺族の居ない、天涯孤独な兵士達のみの密やかな儀式だったリヴァイへの遺書は、やがて遺族が居る居ないに関わらず璧外調査兵団全員の暗黙の儀式となっていた。
それはエルヴィンの耳にも当然入っていた。エルヴィン自身、幾度かリヴァイ宛ての荷物を運ぶ兵士を見ているし、一度はそれを受け取る現場すら目撃した。
扉が開き、荷物のを受渡しを済ませた新兵が頬を紅潮させて閉じられた扉に向かってずっと敬礼をし続ける姿を見たエルヴィンはしかしその新兵に声を掛ける事も、ましてや閉じられた扉を叩くことも出来ずに引き返したことを鮮明に覚えていた。
「人類最強となれ。巨人を駆逐することが夢物語ではないと縋る事の出来るものを、兵士は、人々は求めている。君にはその力がある、リヴァイ。そのための翼は既にその手にある。―――だから、手遅れになる前に。人々が巨人に精神的にも蹂躙されてしまう前に。君が。貌を上げて巨人に挑む様を彼らの目に焼き付けてくれ」
特例中の特例で調査兵団に入団のしたリヴァイは、通常の入団の儀式を行わなかった。代わりにエルヴィンの執務室で、制服を手渡しながらリヴァイに告げた言葉だった。その時、人類の為に心臓を捧げよとは明言しなかった。しかしそれ以上の覚悟と責任と重圧を押し付けたに等しい。
「了解した、エルヴィン」
真っ直ぐに、完璧な無表情で敬礼を返しながらリヴァイは躊躇わずに答えた。
「リヴァイ班は残念な結果になって―――」
「作戦だ。謝らなくてもいい。彼らも納得している」
口調を和らげて労おうとしたエルヴィンの言葉を硬いリヴァイの声が遮った。言葉は冷静で静かだが、その瞳は昏い陰りを帯びていた。
「作戦だと言い切りながらも君は割り切れていないようだね。・・・リヴァイ、ここからは報告ではない君の言葉が訊きたい」
リヴァイの張り詰めた雰囲気にエルヴィンはそっと言葉を掛けてその張り詰めた糸が緩むのを待った。やがてリヴァイの唇が微かに開き、けれども言葉を漏らすには至らずに吐息だけを零した。
「リヴァイ。ここでは人類最強である必要は無い。目を閉じて肩の力を抜け。浮かんだ言葉から順に言えば良い。思考として纏めなくても良い」
ゆっくりと執務机からリヴァイの許へ歩み寄り、右手でそっと瞳を隠す。エルヴィンの掌の下で睫が2,3度揺れた後、動かなくなった。
リヴァイは閉ざされた視界を安寧と受け入れ、エルヴィンの温もりが伝わるに任せた。やがて閉ざされて暗いはずの視界を暖かいものに感じられるようになった頃に小さく心の欠片を落とした。
「俺は巨人を斃す為に調査兵団に入った」
「ああ、そうだな」
「希望になれ、と言われた言葉にてめぇで納得してそうなるべき働きをしてきた」
「君は私が想像していたより遥かに早く、強力に人類と兵士の希望になったと思うよ」
とつとつと紡ぎ出す言葉にいちいち優しく返されるエルヴィンの言葉に、掌の下の眉間に皺が寄り、睫が震えた。
「・・・俺は、そもそもお前に付いてきた時からそうなる事は覚悟の上だったし、何よりそれが俺の希望だった」
「それは違うよ、リヴァイ。君が望んだのは君自身の責任と力で空を翔ける事の出来る翼だけだ。それ以外は私の望みだ」
渡した翼の大きさよりも遥かに重いものを背負わせてしまった自覚のあるエルヴィンは少しでもそれが軽くなれば良いと祈りながら言葉を返す。しかしリヴァイはエルヴィンの言葉にゆるりと首を振った。
「別に今の俺の立場が重いとか苦しいとかは思ってない。どっちにしろ、俺はこういう風にしか生きれない。でもエレンは。・・・エレンはあんな運命想像すらしていなかっただろう」
エレンを監督下に置くに当たって、リヴァイは鎖に繋がれたままの状態のエレンから様々な事を訊き出していた。父親の事、母親の事、巨人と遭遇した時の事。巨人になった時の事。
もともと調査兵団入団希望だったから巨人を斃したいと思う想いは人一倍強い。なのに自分が巨人化すると分かった時の絶望と恐怖を、エレンは膝を抱えながら独り言のように話した。そして最後に「でも、リヴァイ兵長。俺はやっぱり巨人が憎い。もし巨人化して壁の外へ出て自由に生きろと言われても・・・それは出来ない」と呟いた。
身の内に巨人化する能力を抱え、人類から害を成すものとして扱われ、鎖に繋がれているエレンを見てリヴァイは思った。今は恐れ、憎しみの対象ですらある彼がもし巨人化を完全に意図的に行い、その力を人類の為に捧げると誓ったなら。―――人々はエレンを新しい『人類の希望』に祭り上げるだろう。
「エレンは巨人と闘う事は望んでいたが、他人の希望なんか望んじゃいない。まして、自分を護る為に他の誰かが犠牲になる事なんか、あいつにとってはあり得ない事だ」
エルヴィンが言葉を挟む前に畳み掛けるように言い、リヴァイは瞳を覆っている暖かい掌を振りほどく。
軽く顎を上げて自分を睨むように見つめるリヴァイにエルヴィンは振りほどかれた手首を反対の手で握りながら同じように見つめ返した。
君は、自分の肩にかかる重みを知り過ぎる程に知っているから、せめてエレンにはその重みを知らずにいて欲しいと願うのか?
正直、そこまで、と思う。そうまでして救えるものは救いたいと願うこの男はどれ程の覚悟で名前も知らない兵士の遺書を受け取っているのだろう。どれ程の悔しさで命を落とす部下たちの最期を看取ったのだろう。それでもなお忽然と顔を上げて前方を見据える精神の強さは、リヴァイを見つけ出し、人類の希望として送り出した張本人である自分ですら全てを投げ出して縋ってしまいたくなるような何かを持っていた。
「では、訊こう。君は、エレンのように巨人化の能力があるのか?」
「NO」
「エレンの巨人化を無力化する方法を知っているか?」
「NO」
「エレンの身の安全の為にこのまま地下室か何処かに閉じ込めておくか?」
「・・・NO」
「エレンが巨人を洗いざらい打ち負かしてスケープゴートに祭り上げられるのを手を拱いて見ているのか?」
「NOだ!」
ギラギラとした瞳で叫ぶリヴァイは久し振りに見る地下街での本能そのままの姿だった。エルヴィンが矢継ぎ早に放った質問の口調とは一転して柔らかに問い掛けた。
「君はもう答えに辿り着いているよ?リヴァイ」
エレンの身に降りかかるだろう悲劇を予測してそれをどうにか回避したいと思う君なら。自身に掛かる重圧はどれ程重くても構わないと言い切る君なら。理解っている筈だ。
エルヴィンがリヴァイの瞳を覗き込む。
「―――エレンに向くよりも自分により多く人々の目を向けさせろ。『人類最強』として。エレンを護る為に誰かが犠牲になるのが嫌なら君がエレンを護れ。エレンが周りの意思や運命とやらに翻弄されて自分を見失いそうなら、君が前に立って道を指し示してやれ」
言いながら自分の言葉に反吐が出そうだ、とエルヴィンは思った。
自分はまた、この男の抱える荷物を増やしている。理解して、解っているようなふりをして実際は現状を打開するカギと言っていいエレンを死守しろと命令している。
エルヴィンの眉間に皺が寄り一瞬唇を噛んだのを見てリヴァイは緩く微笑んだ。
「―――了解だ、エルヴィン」
口角を上げ、不遜にも取れる微笑みを浮かべたまま、まるで作戦指令を受けたかのように了承の意を表す。
入団したあの日、人類最強と成れと告げた自分に対して返した言葉と全く同じ言葉を同じ調子でリヴァイは返した。
「・・・リヴァイ」
反対に、言ったことを後悔するかのように眉尻を下げ、爪が食い込む程に固く握りしめたエルヴィンが溜まらずリヴァイの名を口にする。それは、今までの上司然とした呼び掛けではなく一人の男として、何処までも強く誰よりも優しい男の心を憂いて。
そんなエルヴィンの握り締めた拳にそっと手を伸ばし、指を開かせるとリヴァイは先程とは異なった優しい微笑みを浮かべた。
「それでいい。お前は俺に命令しろ、エルヴィン。俺が心臓を捧げたのは人類に対してじゃない。この部屋で、お前に捧げたんだ」
目を見開いたエルヴィンを目の端に捉えながらリヴァイは踵を返した。扉に向かって歩きながら「時間取らせて悪かったな」と片手を挙げ、そのまま扉の外に姿を消した。
「君に心臓を捧げられた私の方がよっぼど・・・大きな荷物を持たされたと思うんだが・・・?」
エルヴィンのため息交じりの呟きが執務室に落ちた。
